「イカやタコ、カイは軟体動物です。外とう膜を持つのが共通する特徴です。」と学んでも、しっくりこなかった人もいると思います。イカとタコは同じなかま、というのがわかるようでも、イカとカイでは違うなかまのような気がしませんか。
中学校で学ぶ生物のなかま分けでは、「○○動物」「○○植物」「○○類」という用語がでてきます。一般的によく使われる言い方です。しかしこれだと、「どのくらいの大きさのなかま分けなのか」がよくわからない面があります。
生物を詳しくなかま分けすると、ドメイン(超界)・界・門・綱・目・科・属・種、という階層に従って行うことになります。例えばヒトは、真核生物ドメイン・動物界セキツイ動物門ホニュウ綱霊長目ヒト科ヒト属ヒト(種)
となります。歳後の属と種の名前をラテン語で表すとホモ・サピエンスとなり、この属と種の二つで生物の種名を表したものを学名といいます。
セキツイ動物というのはセキツイ動物「門」、ホニュウ類はホニュウ「綱」という大きさでのなかま分けです。このほか、魚類は魚「綱」、ハチュウ類はハチュウ「綱」というのが正式ななかま分けの名前です。
では軟体動物はどのような大きさのなかまなのでしょうか。軟体動物は軟体動物「門」です。門のレベルの大きさ、つまりセキツイ動物「門」というのと同じだけの大きななかまなのです。そしてイカやタコは「綱」のレベルでは頭足綱、カイは、二枚貝は「二枚貝綱」、巻き貝は「腹足綱」です。ちなみに「流氷の天使」とも呼ばれるクリオネは、殻を失った巻き貝のなかまであり、腹足綱含まれます。
まとめると、イカとカイは、同じ門には属するけれど綱の段階で違うことになります。ヒトにあてはめて考えると、例えばメダカとヒトくらいの違いであると言えます。同じ脊椎動物門ではあるけれど、魚綱とホニュウ綱と綱の段階の違いがある、ということです。
なお中学校では「脊椎動物」に対し、「無脊椎動物」というなかま分けの名前が出てきます。しかし生物学の中では「無脊椎動物」という分類はありません。中学校段階では、脊椎動物以外を便宜的にひとまとめに「無脊椎動物」という呼び方をしているだけなのです。

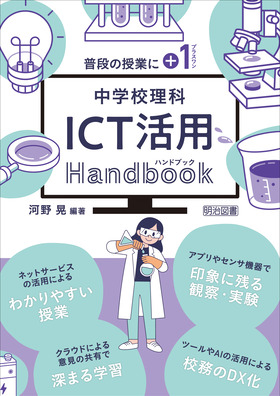

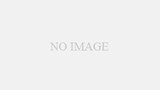
コメント